亡くなった人の借金は払わないといけない?相続放棄で守る方法と注意点
「親が亡くなった後に借金が判明した」「相続したら自分が払わなければいけないの?」
遺品整理や通帳確認の中で突然借金が発覚すると、悲しみの中で冷静な判断ができなくなりがちです。 ですが、亡くなった人の借金を必ずしも相続しなければならないわけではありません。
相続放棄や限定承認といった制度を使うことで“借金を引き継がない”選択が可能です。
この記事では、収入減で生活に余裕がない方でも「亡くなった人の借金から自分の生活を守る」ために必要な手順を、3ステップでわかりやすく解説します。
あわせて読む:公的制度・法的手段 / 借金返済の基礎 / 不安への向き合い方
亡くなった人の借金は相続されるのか?
結論から言うと、相続人が相続放棄をしなければ借金も相続対象になります(民法896条)。 「遺産=プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産(借金)」も自動的に引き継がれる仕組みです。
ただし相続放棄を行えば、借金を含む一切の権利義務を引き継がずに済みます。 また、限定承認を使えば「相続財産の範囲内だけで返済」する選択も可能です。
小まとめ: 何もしなければ借金も自動的に相続されるが、「放棄」すれば背負わずに済む。
相続放棄で借金を引き継がないための3ステップ
STEP1:借金の有無・金額を確認する
まずは「本当に借金があるか」「どこからいくら借りていたか」を把握します。 契約書・通帳・督促状・信用情報(CIC/JICC)などで確認し、一覧表にします。
STEP2:家庭裁判所に相続放棄の申立てをする
相続放棄は原則として“死亡を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申立てる必要があります。 申立書・戸籍謄本・住民票などの書類が必要になりますが、弁護士に依頼すれば代行も可能です。
STEP3:放棄後は借金の請求に応じず、通知のみ保管する
相続放棄が受理されると、請求が届いても支払う義務はありません。 「相続放棄済のため支払えません」という旨を伝え、書面は保管しておきましょう。
ここまでのまとめ: 借金があるか確認 → 3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄 → 以後は請求に応じない、という順番です。
成功事例:相続放棄で借金を引き継がずに済んだケース
事例:父親が亡くなった後にカードローン180万円が判明
通帳や郵便物を確認したところ複数の借入れが見つかり、司法書士へ相談。 死亡を知ってから2か月目に相続放棄を申立て、無事受理。 その後カード会社から督促が届いたが「相続放棄済」の旨を伝えることで請求は止まり、家族は返済せずに済みました。
まとめ|「亡くなった人の借金は相続放棄で防げる」
- 借金も相続の対象になるが、相続放棄すれば引き継がなくて済む
- 死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てが必要
- 放棄後は請求が届いても支払う義務はない
- 迷ったら弁護士・司法書士へ相談するのが最短ルート
この記事を書いた人
借金・債務整理・公的制度に関する記事を300本以上執筆。法テラス・金融庁・消費者庁の公的情報に基づき、「感情→制度→行動」の順番で読者をサポートしています。
2025年8月15日 更新
※本記事は2025年8月時点の情報をもとに構成しています。制度や条件は変更されることがあります。必ず各機関・専門家にご確認ください。


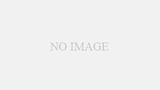
コメント