亡くなった人の借金は家族が払う?ギャンブル依存でも取れる現実的な対処法
「親が亡くなった後に借金の請求がくるかもしれない…」
自分自身もネットカジノで借金を抱えていると、そういった不安が頭から離れなくなりますよね。
結論から言うと、亡くなった人の借金でも“相続放棄”をすれば支払う義務はありません。
ただし、相続放棄には期限(原則3カ月以内)があるため、早めの行動が必要です。
この記事では、
- 亡くなった人の借金が相続される仕組み
- 相続放棄の具体的な手順
- すでに自分に借金がある場合の現実的な対処法
を順番にわかりやすく解説します。
STEP1:亡くなった人の借金は“相続放棄”で引き継がない
民法では、親や配偶者が亡くなった場合でも相続放棄を選択することで、借金を含めた財産をすべて引き継がずに済むことが認められています。
✔ 相続放棄の期限:被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内
この期間を過ぎてしまうと、借金も自動的に相続したとみなされる可能性があるため注意が必要です。
STEP2:自分の借金がある場合は“返済額を減らす”ことを優先
亡くなった人の借金は相続放棄で回避できますが、自分自身の借金は待ってくれません。
返済が苦しい場合、最も現実的な方法は任意整理です。たとえば、200万円の借金+15%の利息がある場合でも、任意整理を行えば利息分60〜70万円をカットできるケースがあります。
STEP3:副業+支出管理で“再発を防止する仕組み”をつくる
返済額を現実的な水準にした後は、副業+支出記録を並行して行うことで、再び借金に悩まされない仕組みを作ることができます。
- スマホ副業 → 月1〜3万円の副収入
- 支出記録 → ギャンブル支出を「毎日1回」書き出す
成功事例:親の死後の借金に悩んでいた30代男性
当時33歳/会社員/借金210万円(ネットカジノ+カードローン)/親の借金50万円
- 親の借金 → 相続放棄で支払い義務なしに
- 任意整理 → 利息60万円をカット
- 副業(データ入力)→ 月28,000円
- 約3年で完済
「親の借金を相続しなくていいと分かったことで、まずは“自分の借金に向き合う覚悟”が持てました」と話しています。
今日からできる3つの行動
- 相続放棄の期限を確認して家庭裁判所に申述する
- 任意整理で自分の返済額を現実的な水準に下げる
- 支出を1日1回書き出し、再発を防止する
著者
借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。


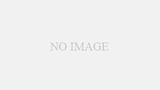
コメント