リボ払いの過払い金は返ってくる?|境界線の見分け方と“返らない時”の最短ルート
「ずっとリボで払ってきた。私にも過払い金は返ってくるの?」——私も返済に追われていた頃、まずここが気になりました。結論から言えば、最近の契約は原則“法定内金利”で過払いが出にくい一方、2010年以前に高金利で契約・運用したリボには回収余地が残ります。本記事の差別化ポイントは、(1)返る/返らないの境界線を一次情報で明示し、(2)返らない場合でも今日からできる次の一手(任意整理+家計再設計)まで具体的に案内することです。私はこの流れで負担を下げ、生活を立て直しました。
まず“仕組み”を押さえる:リボ金利と法改正の関係
リボ払いは毎月の支払額を一定にする一方、利用残高に対して手数料(実質年率)がかかります。2010年6月以降は出資法上限が年20%に引き下げられ、いわゆる「グレーゾーン金利」は撤廃。現在の多くのクレジット会社のリボ手数料は15〜18%前後で、利息制限法の範囲内です。つまり直近の契約だけ見れば“返ってこない”可能性が高い。ただし、改正前に高金利(20%超〜29.2%近辺)で継続利用していた期間があると、当該部分で過払いが発生している場合があります。境界線は「契約・利用の時期と金利」にあります。
| あなたの状況 | 過払い発生の可能性 |
|---|---|
| 2008年以前から年20%超の手数料で長期利用→2012年以降に完済 | あり(検討価値大) |
| 2010年以降に契約・年率15〜18%・延滞なし | 低い(原則なし) |
| 古いカードを更新しつつ使ってきた/契約時期が曖昧 | 要確認(履歴の取り寄せが先) |
「返ってくる」代表例(改正前の高金利用)
例:2005年に年27%のリボ手数料で継続利用→2013年完済。
この場合、法定上限(15〜20%)を超える部分の支払いが「過払い」と評価され、交渉や訴訟で回収できることがあります。完済時期が古いほど時効の壁に近づくため、完済から10年・“知った時”から5年の消滅時効に注意が必要です。
「返ってこない」代表例(近年の法定内リボ)
例:2016年に年率18%でリボ契約→現在も利用中。
利息制限法内の手数料であれば過払いは原則発生しません。広告に左右される前に、まずは利用明細で手数料率と契約時期を確認し、無いものに時間をかけない判断が重要です。
▶ 匿名OK|契約時期と金利から「過払いの余地があるか」を無料チェック
確認の3ステップ:履歴→再計算→方針決定
- 取引履歴を取り寄せる:カード会社に開示請求。信用情報の本人開示(CIC/JICC)で他社の契約も一覧化しておくと精度が上がります。
- 利息制限法で再計算:どの期間・いくらが法定超過かを把握。家計の現状シートとセットで数字を見ます。
- 交渉 or 訴訟 or 撤退:回収見込みが薄いなら過払い請求に固執せず、リボ残高が重い人は任意整理で将来利息カット+36〜60回の再構成へ切り替えます。
私は③で「撤退+任意整理」を選び、督促が止まった瞬間に心が軽くなりました。以後の連絡は代理人宛となり、月額も家計の範囲に収まりました。
▶ 今日中にやること:履歴請求のメモ+家計シートDL(無料テンプレ)
“返らない”と分かったら:最短で負担を下げる三位一体策
「過払いで一発逆転」を待たず、返済負担を下げる・収支を整える・再発を断つを同時に回します。①任意整理(将来利息カット+分割再構成/手続きの流れを確認)②固定費の最適化(通信・保険・サブスクの年次棚卸し)③副収入の上積み(在宅ワーク等で月+1〜2万円)④衝動・依存のトリガー対策(買い物・ギャンブル癖の回避設計)。「月2万円の余力×36か月」で72万円の返済原資が生まれ、心理的な余裕も戻ります。
成功事例:2005年契約→80万円回収/2016年契約→任意整理で月2.1万円まで圧縮
①40代女性(私の相談者)。2005年に年27%でリボ、2013年完済。履歴開示→再計算→和解ベースで約80万円回収・3か月、報酬等控除後の手取り約62万円。「教育費の穴埋めができた」と安堵。
②30代男性(私自身が体験)。2016年契約・年18%で過払いは0円。ただし残高が重く、任意整理で将来利息をカット。月3.8万円→2.1万円×60回に再構成し、固定費−1万円と副収入+1.5万円で黒字化。「“戻るかも”に賭けるより、確実に下げる方が早い」と納得できました。
参考・出典
出典:法テラス/金融庁/CIC/JICC(2025年9月時点) 更新日:2025年9月3日
著者
借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。


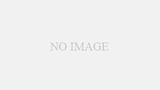
コメント