亡くなった人の借金はどうなる?相続放棄でギャンブル債務を背負わない方法
「親が亡くなったが借金があるかもしれない」「ギャンブルで作った借金まで相続するのか?」──大切な人を失った後に借金の問題が浮上すると、不安で眠れなくなりますよね。
結論から言えば、亡くなった人の借金は相続人に引き継がれます。ただし、相続放棄や限定承認という制度を使えば、借金を背負わずに済む方法があります。
この記事でわかること
- 亡くなった人の借金はどう扱われるのか
- ギャンブル債務も相続されるのか
- 相続放棄・限定承認で回避する方法
- 相続後に借金が判明したときの対処
亡くなった人の借金は相続される
結論:財産と同じく借金も相続されます。
民法では、亡くなった人(被相続人)の財産と借金はすべて相続人に承継されます。つまり、プラスの資産(預金・不動産)だけでなく、マイナスの資産(借金)も引き継ぐのです。
借金の理由が生活費でもギャンブルでも関係なく、契約に基づく借金は相続対象となります。詳しくは → 債務整理と制度解説 をご覧ください。
相続=財産と借金の両方を引き継ぐ行為です。
ギャンブル債務も相続対象になる?
結論:はい。理由に関係なく借金は相続されます。
「ギャンブルで作った借金だから免除されるのでは?」と思う人もいますが、法的には関係ありません。借金契約が存在すれば、相続人に引き継がれます。
ただし、借金が多すぎて返済不能と判断した場合は、相続放棄や限定承認を利用すれば回避できます。
借金の理由は問われず、相続される。ただし制度を使えば背負わなくて済みます。
相続放棄と限定承認の仕組み
結論:相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ手続きが必要です。
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの借金も一切引き継がない方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲で借金を返済し、それ以上は負わない方法
どちらも相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります(出典:法テラス/2025年9月時点)。
3か月以内の判断が、借金を背負うかどうかの分かれ道です。
成功事例|父のギャンブル債務300万円を相続放棄で回避
結論:家庭裁判所で相続放棄を行い、借金を負わずに済みました。
私の知人は父親が亡くなった際、300万円の借金が発覚。相続放棄を家庭裁判所で行い、借金を一切相続しませんでした。その結果、生活を守ることができました。
相続放棄の具体的な流れや書類の準備は → 借金返済の基本 を参考にしてください。
相続放棄をすれば、ギャンブル債務でも背負う必要はありません。
再発防止|家族が借金を残さないために
結論:借金を残さないためには、生前からの準備が重要です。
- 任意整理:借金を整理し、返済計画を明確にする
- 家計改善:固定費を削減し、将来に備える
- 依存対策:ギャンブル依存症の治療や相談を活用(出典:厚生労働省/2025年9月時点)
不安が大きい場合は → 借金苦で悩むあなたへ をご覧ください。
「亡くなった人の借金」は避けられますが、「生きているうちの返済計画」こそ大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 亡くなった人の借金も相続されますか? A. はい。財産と同じく借金も相続対象です。 Q. ギャンブルで作った借金も相続するのですか? A. はい。理由に関係なく借金契約があれば相続されます。 Q. 借金を相続しない方法はありますか? A. 相続放棄または限定承認を、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で行えば回避できます。
最終更新日:2025年9月12日
著者
借金ゼロ教室を運営するみろく。20代で300万円の借金を抱え、任意整理+副業+固定費削減の3本柱で2年で完済。現在は「返済負担の軽減」「副業による再建」「一次情報に基づいた債務整理・支援制度の解説」を軸に情報発信し、返済相談や節約アドバイスのオンラインサポートも実施。記事はすべて法テラス・金融庁・CIC・JICC等の公式情報を確認したうえで執筆・更新しています。


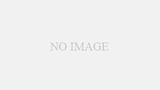
コメント